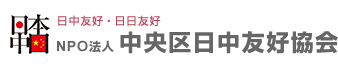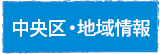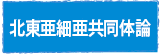北東亜細亜共同体論
減反廃止に地域政策の不在を見る (2025.09.29)
減反廃止に地域政策の不在を見る
- 中國の地域振興政策
はじめに、社会主義中國の地域政策を見てみよう。下の図が、その政策の結果である。
これは、中国の省別人口の推移を、最近の2017~2023年について見たものである。コロナ禍を契機にして、中国経済が停滞期に入った時期である。
人口数は、国の勢いを最も忠実に表す指標である。だから、日本では人口調査のことを国勢調査と言っている。
この図から分かることは、中国が西部の農村地域へ大胆な人口移動を行っていることである。
これは、沿海部の大都市地域への人口移動による過密化を避けるためだけではない。農村地域の振興による国土の均衡ある発展などという訳の分らぬものでもない。農業の発展による食糧安保のためである。そのために、地域社会全体の活性化を図ったものである。
かつて、毛沢東が言ったことがある。大都市に原爆が落とされても、地方は他の地域に依存することなく、まして、他国に依存することもなく、自立して生き残るのだと。そのために、食糧自給率を95%にまで高めておくのだと。それほどまでに、国家の独立を重視してきた。
中国の地域振興政策は、地域の共同体を基礎にした、国家の安全保障政策だったのである。
- 日本はどうか
上の中國の図の下に描いてある、日本についての同様な図を見てみよう。
日本では、農村地域が軒並み人口を減らしている。増やしているのは、東海道沿線の都市地域とそれに続く都市地域だけである。これは、いまの地域政策の結果である。日本の政治家は、これでいいのだ、と考えている。
政治家だけではない。その周囲の評論家も、他人事のように考えている。そして、あと何年でこの地域は消えてなくなるなどと計算して、偉そうに、しかし緊迫感を欠いた発言をしている。
ここには、食糧安保の考えは、そして、国家安全保障の考えは微塵もない。
- 減反廃止は農村地域の振興による食糧安保のために
石破 茂首相と小泉進次郎農相による減反廃止政策と、大規模機械化農政は、このことと深く関わっている。
この2つを一体にした農政は、米価の暴落と暴騰を繰り返すだろう。その結果は、消費者のコメ離れを招き、コメはパンやメンに主食の座を奪われるだろう。そして、主食さえも輸入に依存することになる。
一方、生産者は、それに耐えられる平野部の大規模農家だけが生き残り、中山間地の小規模高齢農家は見捨てられて、その地を去るだろう。
日本の農村地域が、このようになるのは、いまの農政の結果である。それは、政府だけの責任でなない。野党に、この農政に対置する農政がないことも大きな原因である。
- 目指すべき地域政策としての農政
中山間地についての、いまの農政に対置すべきものは何か。
それは、確固とした地域政策である。それは、農業者だけが地方に住んで、農業だけを営んでいればいい、というものではない。
中国のように、農業者以外の人たちも一緒になって、みどり豊かな森や農地に囲まれて、経済活動を楽しむようにする政策である。
先端的な産業も取り入れるし、大企業も誘致する。近くには、品揃えの整った商業施設も集まってくるし、文化施設もやって来る。そこには、若者も大勢いて、高齢者といっしょに目を輝かせて、農業だけでなく、経済活動だけでもなく、多くの社会活動、文化活動も行っている。
それは、100年前に、若き武者小路実篤たちが夢に描いた、理想の協同社会に近いのかもしれない。
こうした地域政策こそが、目指すべき政策ではないか。そして、農政ではないか。
. ( JAcom から転載))