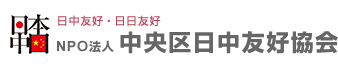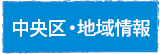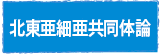北東亜細亜共同体論
「保守」と「協同」の排他性と近親性 (2025.10.06)
「保守」と「協同」の排他性と近親性
- 「保守」の曖昧さ
政治の季節が、いまその真っ只中にある。一昨日は、自民党の総裁選挙が行われ、高市早苗氏が選ばれた。これで一区切りがついたようだ。だが、多党化の中で、自民党総裁が総理大臣になれるかどうか、は分からない。これからも熱い政治の季節は続くだろう。
高市氏は、一部で「強硬保守」といわれている。「強硬」は後半の主題にするが、「保守」とは何か、が分からない。
そうしていま、政治のなかで「保守」という曖昧な言葉が蔓延している。そして、多くの政治家と政党が、保守を自称している。野党さえも、その多くが「保守」を自称している。
だが、「保守」は政治哲学としての定まった概念ではない。だから、意味不明のままで勝手に踊っている。一部の政治家にとって、変幻自在で都合のいい言葉なのだろう。
- 誰のための「保守」か
「保守」の意味だが、その多数説は、古き良き伝統や文化を守る考えだ、という。だが、「良き」ものさえも否定する乱暴な論者はいないだろう。また、これは文化論であって政治哲学ではない。
政治哲学としての問題の所在は、ここではない。政治家が、この曖昧さを利用することである。
政治家は、政治哲学からみて、誰にとって「良き」なのか、を言わない。「国民にとって良き・・・」と踏み込んだフリをする人もいる。
だがこの場合、「国民」とは誰なのか、を言わない。農業者も労働者も資本家も、ひっくるめて「国民」というのか。それでは何も言ったことにならない。せいぜい非国民を除く、という程度でしかない。それはそれで問題である。
- 国民とは誰のことか
さて、「国民」とは誰のことか。国民のごく一部の資本家のことか、それとも国民の大多数である農業者と労働者のことか。政治論としては、ここが最も峻別すべき基本的な分かれ目である。
そして、資本家による農業者・労働者に対する間接的・直接的な搾取を強めるのか、弱めるのか。強めるのなら資本主義だし、弱めるのなら社会主義である。
ここを曖昧にする保守政治家は、国民を欺くものである。
- 「保守」と協同組合
「保守」には、もう1つの説がある。それは、理性的な判断は必ずしも無謬ではないから、古くからの長い間、事実として無謬だったことを多くの人が認めれば、それは守ろう、という考えが保守だ、という評論家がいる。
これは政治哲学ではない。しかし、民主主義の根本にある哲学である。ここには、協同主義と通底するものがある。
- 全員一致は民主主義の神髄
協同主義と通底するものは、共同体の長い歴史の中で培われ、規範としてきた全員一致の原則である。これは、今後も守っていこう、という考えである。民主主義の欠陥を是正する1つの有力な方法である。
かつて、島根の萬代宣雄氏が94%の賛成を得て農協の組合長になったとき、就任の挨拶で、「6%の人たちからも賛成を得られるような運営をしたい」と言った。これは民主主義の神髄だろう。
- 金の宰相へ
この点が「強硬保守」といわれる高市氏の「強硬」の部分に関わってくる。
全員一致で「強硬」が支持されるならいいだろう。せめて94%の支持があるなら、それでもいいだろう。いま高市総裁は、日本を代表する総理大臣になろうとしているのである。せめて94%程度の支持が得られるような政治を行ってもらいたい。そうなれば、高市氏は鉄の女宰相といわれたサッチャー氏を超えて金の宰相といわれるかしれない。
そして、もしも高市氏が新総理になったとして、農協大会や労組大会に招かれたら、そこで民主主義の神髄に触れるような挨拶をすれば、「強硬」という汚名は晴らせるだろう。その上で、農業者・労働者の代弁者であって、資本家の代弁者でないことを明言すれば、熱烈に歓迎されるだろう。
. (2025.10.06 JAcom から転載)