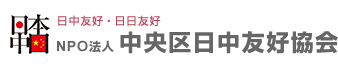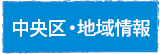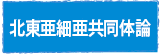北東亜細亜共同体論
与党の敗因は、反農協と食糧安保軽視の市場原理主義農政 (2025.07.21)
与党の敗因は、反農協と食糧安保軽視の市場原理主義農政
- 国民の審判が下った
国民の厳正な審判が下った。一昨日の参院選の結果は、政権与党の過半数割れだった。
この結果をもたらした大きな原因に、小泉進次郎農相の農政があった。1、000万人の農協組合員と、それにプラスされる数百万人の家族の多くは、小泉農政を支持しなかったのではないか。
それは、東北各県など農業県での不振に見られた。もしも、東北だけでも互角の勝敗だったら、過半数割れの憂き目を見なかった計算になる。
支持しなかったのは、小泉農政のどの部分だったのか。
参院選が終わり、政治の激動期に入ったが、ここで暫し立ち止まり、与党の敗因は何だったのかを、その根本にまで遡って考えてみよう。
- 小泉農政は市場原理主義農政だ
小泉農政の根本には、市場原理主義がある。市場に全てを任せて、政治は市場に一切介入しない、という考えである。そうして、市場原理主義で農政の全てを塗り潰す。市場原理に背くものは、すべて排除する。そういう考えである。
この考えは、協同組合主義の全否定である。
そしてまた、この考えは、主食であるコメさえも外国に依存し、日本の食糧安保の危機を深め、国家としての存続を危うくするものである。
- 農協の全否定
農協との関係について、具体的に見てみよう。以下が、小泉農政の主な点である。
- 1.共同販売から買い取り販売へ
- 2.農機の共同購入からレンタルへ
- 3.農協の株式会社化
- 4.部門別の独立採算制で不採算部門の切り捨て
これらは全て協同組合の根本的な否定である。そして、日本が世界から賞賛されている総合農協という特質の否定である。
そもそも、協同組合の存在理由は、資本による労働の搾取を否定するところにある。だから、カルテルなどの独占行為を、独禁法の適応除外にしている。全ての法治国家は、それを法認している。しかし、小泉農政は法認しない、というのだろうか。
それでは、両者は全面対立になる。
- コメ問題にみる食糧安保の軽視
コメ問題について見てみよう。
昨年からの米価高騰問題で露わになったことは、小泉農政の食糧安保の軽視である。それは、国家主権の放棄に連なる。
米価を下げるというのだが、それでは離農が加速するだけだ。だから供給量が減り、米価は下げられない。消費者のコメ離れも加速する。
小泉農政には、ここに危機感がない。どうするというのか。
- 1.農業経営を大規模化して生産コストを下げる
- 2.農業者を収入保険に加入させる
- 3.増産して輸出する
- 4.過剰分は飼料にする
ここには、大規模化が出来ない中山間地稲作の放棄がある。それは、主食の国内自給率の大巾な低下を結果する。食糧安保の軽視である。資本に国境はない、という市場原理主義であり、自己責任を強いる市場原理主義である。
また、輸出については、実現できる根拠がない。飼料化については、具体的な法制の拡充について、口を閉ざしている。だから、本気かどうか、が疑われる。
- 農業者・農協と議会制民主主義の力
こうした中で、一昨日、国民の審判が下った。その結果は、与党の惨敗だった。
これをみて、市場原理主義の資本主義のもとでも、議会制民主主義は、まだまだ力を持っている、と考えるのは、早計だろうか。農業者と農協には政治を変える力がある、と考えるのは早計だろうか。
早計ではない。1、000万人を超える農業者と農協、および議会制民主主義は、政治を変革する力を持っている。
その力を、発揮しているのが、山田正彦元農相などが行っている「百姓一揆」に参加して、「時給10円」に抗議の声を上げている人たちである。
一昨日の政治の激変は、議会制民主主義のもとでも、こうした運動が、閉塞した社会を変革する力になることを証明した。
このような力で、市場原理主義農政は、やがて消え去るだろう。
一昨日の国民の審判は、近い将来における、そのことを予感させるものだった。
. (2025.07.22 JAcom から転載)